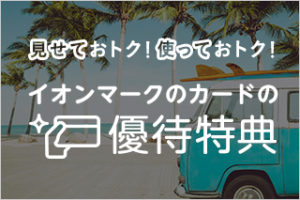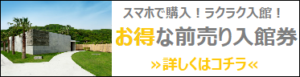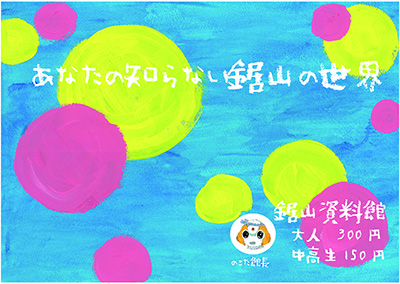展覧会情報
彫刻に触れるとき/2026 桒山賀行彫刻展
主催: 公益財団法人 鋸山美術館
後援: 富津市、富津市教育委員会、社会福祉法人日本点字図書館、共英製鋼株式会社
協力: 筑波大学芸術系彫塑研究室、東海大学文明研究所
お問合せ: 公益財団法人 鋸山美術館
〒299-1861 千葉県富津市金谷2146-1
電話: 0439-69-8111
FAX: 0439-69-8444
E-mail: voice@nokogiriyama.com
HP: https://nokogiriyama.com
Informations
| 展覧会: | 彫刻に触れるとき/2026 桒山賀行彫刻展 |
| 会期: | 2026年1月2日(金)~5月10日(日) |
| 開館: | 10:00 - 17:00(入館は16:30まで) |
| 休館日: | 毎週火曜日定休(火曜日が祝日の場合は翌日/ゴールデンウィークは開館) |
| 観覧料: | 一般800円/中高生500円/小学生以下無料/障害者手帳をお持ちの方無料/団体20名以上1割引 |
| 記: | 本展は公益財団法人野村財団の助成を受けて開催されています。 |
彫刻に触れるとき/2026 桒山賀行彫刻展
日本の具象彫刻を代表する木彫家
桒山賀行は、高村光雲から数えて四代(高村光雲-山本瑞雲-澤田政廣-桒山賀行)、伝統の系譜に位置する彫刻家である。
1966年、愛知県立瀬戸窯業高等学校を卒業した桒山は、同年に澤田政廣の内弟子となり木彫のいろはを学び、早くから頭角を現した。
2007年、第39回日展において内閣総理大臣賞を、2023年には令和四年度日本芸術院賞を受賞し、名実どもに現代日本を代表する木彫家となった桒山だが、12年間に及ぶ修行期から今も変わらず、独自の木彫表現を追究し続けている。
本物の木彫作品をすべての子どもたちへ
1992年、桒山は視覚に障がいのある友人にも楽しんでもらおうと、作品に触れることのできる彫刻展を開催した。
以来、30年以上にわたり「手で触れて見る彫刻展」を継続し、2025年には第34 回展を迎え、世界的にも希有な実践となっている。
そして、2026年、新たな「触れる彫刻プロジェクト」が始動する。「触れる鑑賞」のための作品を桒山賀行が制作し、筑波大学芸術系彫塑研究室・東海大学文明研究所と連携して、全国の盲学校・視覚特別支援学校に本物の木彫を届けていく。
展覧会フライヤー
展覧会名:彫刻に触れるとき/2026 桒山賀行彫刻展